3月2日(土)、3日(日)、2024年最初の学会参加として、朝日大学(岐阜県瑞穂市)で開催された日本コーチング学会第35回学会大会に参加してきました。

私の参加目的は、
講師としては「伝え方のヒントを見つける」、
ライターとしては「情報分析に限らず取材ネタを探す」、
業者としては「Vosaicを使ったご発表を聞き、ご意見を聞く」ことです。
Vosaicを国内展開して4年、学会発表や投稿論文を出していただけるようになりました。「使ってますよ」という言葉をいただくために仕事をしている、そう言ってもいいくらい嬉しいことです。
学会のテーマは「コーチング学と実践現場をつなげる ~長良川における汽水域の如く~」です。
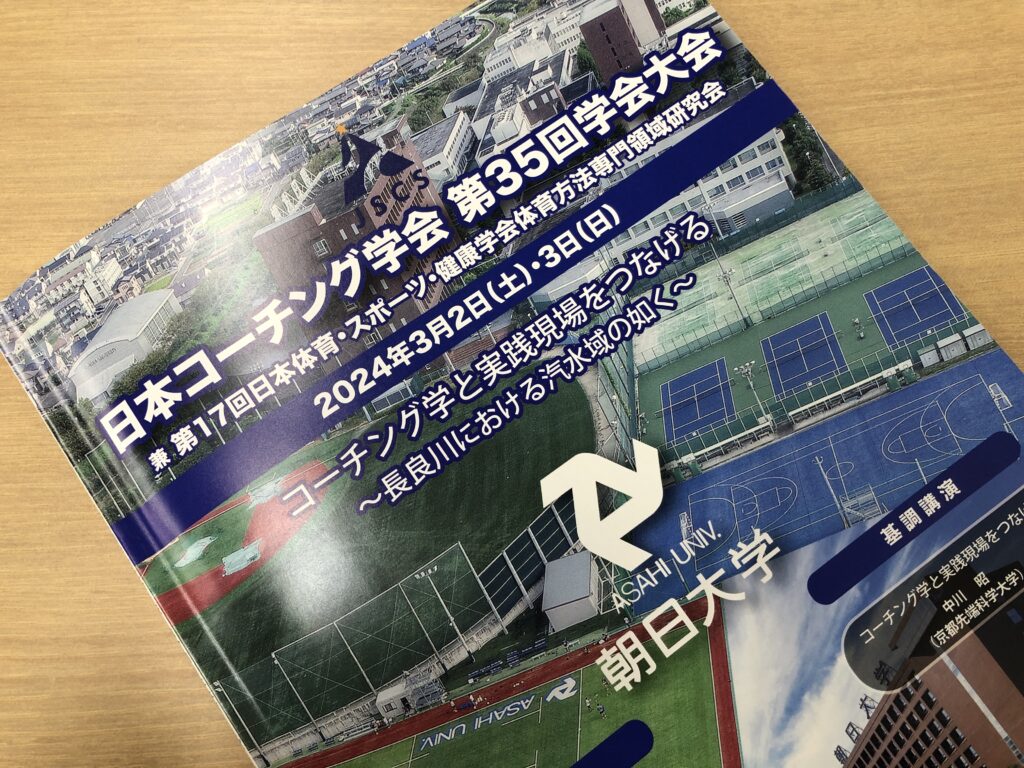
この「汽水域」という表現、釣り好きの私の心に響きます。
汽水域
淡水と海水がまじりあっている状態を汽水といい、河口や湧き水のある海中など塩水・淡水の両方から構成されている水域を汽水域と呼ぶ。独特の生物が見られる特異な場所でもある。(コトバンク)

振り返ると最初に就職した放送局で「報道番組ディレクター」という、ニュースと番組の狭間の「汽水域」とも言える職種に就いた時から、「中間に位置しつつ、多様な視点を持つ」ことを意識するようになったのかなと思うことがあります。
「狭間」と言えば、もう1つ印象に残っている言葉があります。
「あえて狭間にいるからこそ、見えるものがある。」
2022年公開の映画『シン・ウルトラマン」の主人公の台詞です。
これも映画館で聞いた時から、ずっと心に残っています。
私はコーチングの現場こそ持っていませんが、授業も1つの実践の場だと思っています。
「支援者」「教育者」「取材者」の間の「汽水域」に居ること。ときには中途半端に見えるかもしれませんが、このことを自分だけの価値に変換できたらと思っています。
(橘 肇/橘図書教材)
